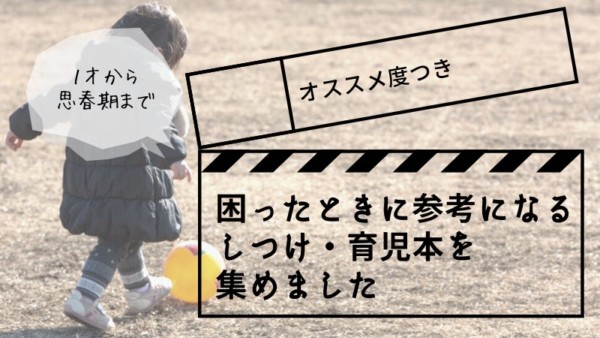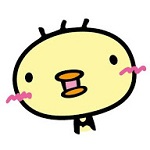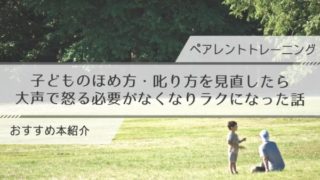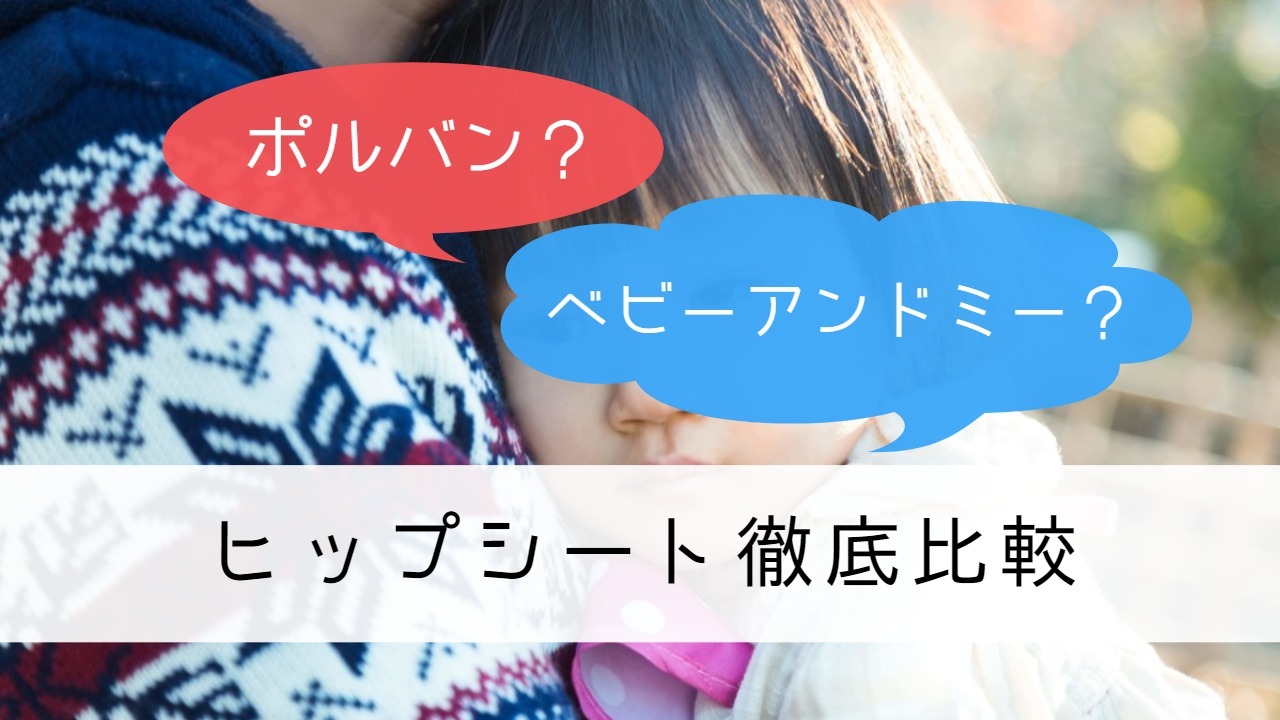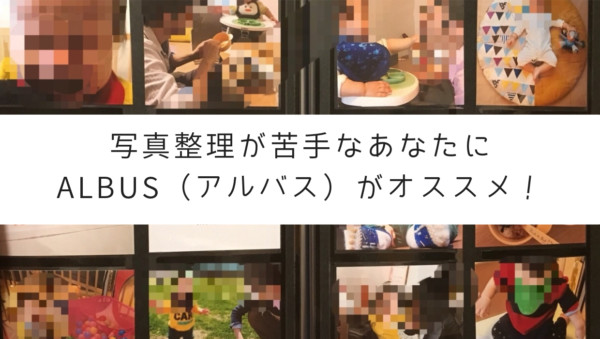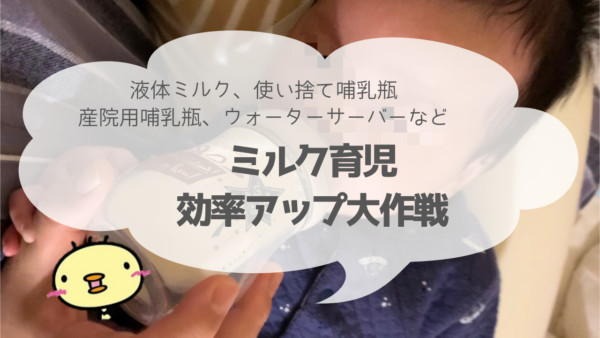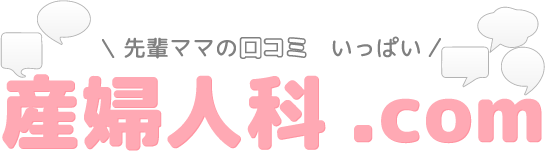日に日に主張が増えてきた息子。嫌なことがあると道端に転がったり、物を投げたり・・・対応に追われグッタリな毎日です😅
この記事では、我が子の対応に悩んだときに役立つしつけ・育児本をご紹介します。
子どもの「いや」に困ったとき読む本~どうやってしつければいいの?~
まずはこちら、タイトルからしてイヤイヤ期ど真ん中な本です。

おすすめ度
冒頭に子どもの脳の仕組みについて解説があり、それを実際の場面を挙げてQ&A方式で実践していく形で書かれています。
- 子どもが「いや」と言うのは、命を守るための本能的な賢さ〈いやいや脳〉が機能しているから
- 〈いやいや脳〉と、言葉を理解して言うことを聞こうとする〈おりこう脳〉が葛藤して「がまんする力」を身につける
- 「がまんする力」を育てるためには、子どもが不快な時に「安心・安全」を与えること
具体的に挙げられていたのはこんな場面。
- すべり台を怖がる
→ 「こわいね、よく言えたね」と認める - 食べ物をオエッとして食べない
→ 〈いやいや脳〉がちゃんと機能してえらい、と捉えてのんびり構える - 転んで大泣きする
→ 痛いという気持ちに共感し、安心して泣けるようにする
まずは〈いやいや脳〉を認め、「安心・安全」を与えた上で気持ちの切り替えをするのが大切なんですね。
後半では、そこまでの内容を踏まえでどんなふうに「しつけ」をしていけばいいか書かれています。
個人的にはしつけという言葉があまり好きではありませんが、子どもへの伝え方としてすごくわかりやすい!1~3歳頃のお子さんをお持ちの方に、ぜひオススメしたい一冊です。
ただ一点だけ、「親向け」ではなく「ママ向け」に書かれていたのだけが残念ポイント。「ママたちの質問に答える」「ママが一番」の表現はなくてよかったなぁ・・・
- 著者は臨床心理士
- ほぼ文章のみだが、実例が多く読みやすい
- 「わかりやすいルールが欲しい」「子どもの対応に困ったときの考え方が知りたい」人にオススメ
ADHDのペアレントトレーニング むずかしい子にやさしい子育て
どうにかして怒鳴るのをやめたい、ちょっと手間がかかってもいいから子どもとの関係を見直したい。
そんな方にオススメなのがこちら。

おすすめ度
タイトルに「ADHDの」とありますが、もともとADHDの子どもを持つ親を対象に書かれたものではありません。
子どもの行動を「してほしい行動」「してほしくない行動」「許し難い行動」の3つに分類し対応法を実践する、ワーク形式の本です。
少し手間はかかりますが、本に書かれたステップ通りに進めることで、子どもとの関係は確実に変わります。くわしくはこちらにまとめました👇
- 著者は神経精神医学研究所スタッフ
- ワーク形式で、実践しながら少しずつ読み進める
- 「怒ってばかりの自分を何とかしたい」「子どもとの関係を見直したい」人におすすめ
発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル
「ADHDのペアレントトレーニング」に興味がある、でもワーク形式をがんばって進める時間と気力はない。そんな方にはこちら。

おすすめ度
こちらもタイトルに「発達障害」とありますが、どんなお子さんにも広く役立つ本です。
ほめる・しかる・伝える・励ますなど、項目ごとに様々なチェンジスキルが紹介されています。
- 最後にほめる ⇒ 途中でもほめる
- よくない行動をやめさせる ⇒ 適切な行動に「置き換える」
- 注意や禁止に強い言葉を使う ⇒ 提案してみる
などなど、少し意識すると子どもとの関係を見直せるポイントがたくさん。
文字が大きくイラストも多いので、本を読むのが苦手な方や時間がない方にもオススメです。
- 著者は大学院教授、発達支援に長年携わり、講演会や研修会の講師を務めている
- 文字が大きくイラスト多め
- 「困った時に使えるワンポイントアドバイスが欲しい」「長い本を読むのは苦手」な人にオススメ
ママも子どもも悪くない!しからずにすむ子育てのヒント
続いて、発達障害が専門の臨床心理士さんが書かれた本。親向けのセミナーで反響が大きかった内容がまとめられています。

おすすめ度
ふんわりしたアドバイスではなく、具体的な子どもとの向き合い方・考え方がわかりやすくまとめられています。
図解も多く、悩み相談ではなくHOWTO本といった印象。
特にいいなぁと思ったのは、子どもの行動を「聞こえてない」「うっかり」「わからない」「わざと」の4つの視点から考えるという方法。しかる前にまずは子どもの立場で考え、その上で対応法を考えます。
- 単純に「聞こえていない」
→ 近くから子どもと目を合わせて話す - 悪気はないが「うっかり」すぐに忘れてしまう
→ 何をやるんだっけ?など一緒に確認する - やるべきこと・言われている意味が「わからない」
→ 具体的に説明したりやってみせるなどしてわかりやすく伝える - 注目されたくて「わざと」やっている
→ スキンシップをとるなど向き合う時間をとる
うまく分類できなくてもそれはそれでOK!
- まずはいろいろな視点から子どもを見てみる
- 4つの視点は子どもの思いに近づくキッカケのひとつと捉える
という考え方に魅力を感じました。
大切な部分は本全体を通してくりかえし説明してくれるところも良い。いろいろな事例で応用しているうちに、自分の中に落とし込んでいける気がします。
- 著者は発達障害を専門とする臨床心理士
- 図解・イラスト多め
- 「精神論ではなく理屈で教えてほしい」「育児全般に応用できる考え方が知りたい」人にオススメ
1歳からはじまる困ったわが子のしつけと自立
続いては『1歳からはじまる困ったわが子のしつけと自立』
現役保育士・幼稚園教諭からの具体的なアドバイスが多く載せられています。

おすすめ度
悩みごとにそれぞれ見開き1ページ。
右ページに簡単な解説、左ページは「こうしてみよう」と具体的な方法をポイントに分けて説明。イラストも多く、気になるところからサクサク読めます。
たとえば「2才1ヶ月の娘がなんでも嫌と言って親の言うことを聞かない」という悩みに対しては、
厄介ですが、お母さんを困らせようとしているわけではありません。このころの「イヤ」は、自分というものを意識しだした印なのです(略)「イヤ」は順調に成長している証で、むしろ喜ぶべきことなのです。
という解説のあと、
- ポイント1「イヤに反応しすぎない」
- ポイント2「子どもの気持ちを聞いてみる」
のふたつに分けて、声かけ方法や向き合い方が説明されています。相談によっては「それでも困った時には」コーナーがあるのもなかなかいい。
- 現役保育士・幼稚園教諭のアドバイスを心理学教授が監修
- イラスト多め、コラム形式で読みやすい
- 「事例に対する具体的な解決法を教えてほしい」「発達をふまえた声かけが知りたい」人にオススメ
子どもが聴いてくれる話し方と 子どもが話してくれる聞き方大全
続いては、口コミ評価がとっても高いこちら。
対象年齢は息子よりやや高め(会話がしっかりできる子がメイン)ですが、息子との向き合い方に関してとてもとてもお世話になっています。

おすすめ度
タイトル通り、この本は子どもに対する「話し方」と「聞き方」を学ぶ本。「子どもの気持ちを否定せず尊重し、自分で気持ちを処理するのを助ける」ための向き合い方が書かれています。
たとえば私がハッとしたのはこんな部分。
私は子どもたちに、自分の知覚を信じるのではなく、私の知覚を信じなさいと、何度も何度も言っていたのです。
(略)
「自分が、疲れている、暑がっている、退屈している子供だと思ってみたら? そして、私がどんな気持ちなのかを、私の生活の中でとても大切な位置にいる大人に、知ってもらいたいと思っていたとしたら・・・?」
毎日の生活に追われていると、
「プラレールはもういいから早くこっち来て」
「その動画はもう何回も見たでしょ」
なんて思ってしまうときがあります。
でも、息子は息子なりに自分の思いを一生懸命訴えている。それを「私の知覚」で否定してはいけない。
息子の気持ちを尊重し認めることで、自分で切り替えることができたかもしれない。たとえ同じ結果になったとしても、まずは一言、息子に沿った声かけをしてあげればよかった。
改めてそんなことを考えました。
この本は、親を責めたり否定したりすることはありません。
筆者さんも失敗しながら、ワークショップの他の保護者さんの失敗体験も交えながら、少しずつ会話スキルを磨いていく本です。
- 子どもがひどいことを言ったとき、共感してあげられない時はどうしたらいいか
- アドバイスはしてはいけないのか
などなど、これから息子が成長するにつれてぶつかるであろう問題がたくさん。
今は基本的な考え方や子どもとの向き合い方を勉強しつつ、数年後に備えて読み込んでいきたいと思います。
- 著者は児童心理学を学び、家族の問題についてワークショップを行う元大学職員
- ワークショップ(体験講座)形式・翻訳本なのでやや読みにくく感じるかも
- 「子どもとの向き合い方を改善したい」「本を読みながら実践したい」という人にオススメ
佐々木正美先生の子育てお悩み相談室
続いて、育児に悩む親向けにたくさんの本を出版されている佐々木正美先生の「子育てお悩み相談室」
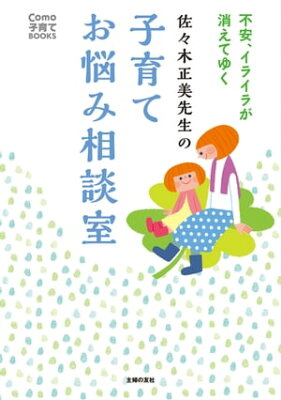
おすすめ度
「お悩み相談室」というタイトル通り、親からの質問にひとつひとつ答えていく内容です。「具体的な悩み解決方法を提示」というより、隣に座って語りかけてくれるようなイメージ。
たとえば「わが子とほかの子を比較してしまう」という悩みに対しては、
私は、このお母さん自身、親に比較されて育ったのではないかと感じます。「自分はどんな自分でもいいのだ」という自己肯定感を、十分に育てられないままお母さんになってしまわれたのではないでしょうか。
息子さんへの態度を変えたいと思うのであれば「一生懸命やればそれでいい、結果は問わない」と心に決めてください。そして実際にそのようにふるまうのです。
「3才長男の人見知りが心配」という相談には、
いまお母さんがすべきことは、本当の意味でこの子を喜ばせることです。
(略)
どうぞ、「この子はこの子のままでいいんだ」と、本気で思ってください。お母さんの信頼と安心こそが、子どもがのびのび育つ土壌になるのです。
といったかんじ。
もちろん発達を踏まえたアドバイスも多くありますが、どちらかというと精神的にふんわり受け止めてほしい・語りかけてほしいという方向けな本だと思います。
あとがきには、
うんと手をかけてください。
うんとかわいがってください。
必ず、いい子に育ちますよ。
と書かれていました。
素直に受け止めて力をもらえるか、いやいやそれができないから困ってるんだよ!と感じるか・・・自分の精神状態によっても違ってきそうです😅
もちろん、佐々木先生の言葉に救われる方も多いはず!
向き不向きがあると思うので、レビューを見てから購入するのがいいかもしれません。
- 著者は有名児童精神科医
- ほぼ文章のみ、一部イラストあり
- 具体的な悩み解決法より「寄り添って語りかけてほしい」人にオススメ
子どものしつけ・育児のおすすめ本│まとめ
育児本は星の数ほどあり、やり方もそれぞれ。自分に合う本を見つけるのってなかなか大変なんですよね・・・今後も気になるものはどんどん読んで、紹介していきたいと思います。
今のところ一番のオススメはこれかな👇