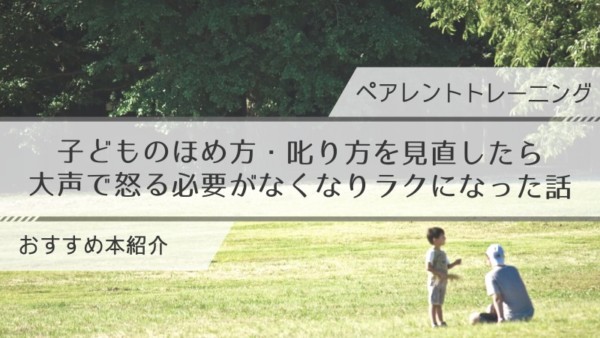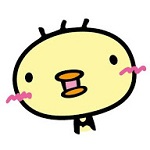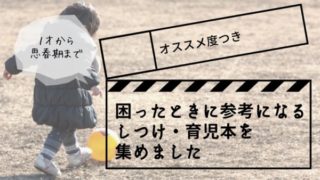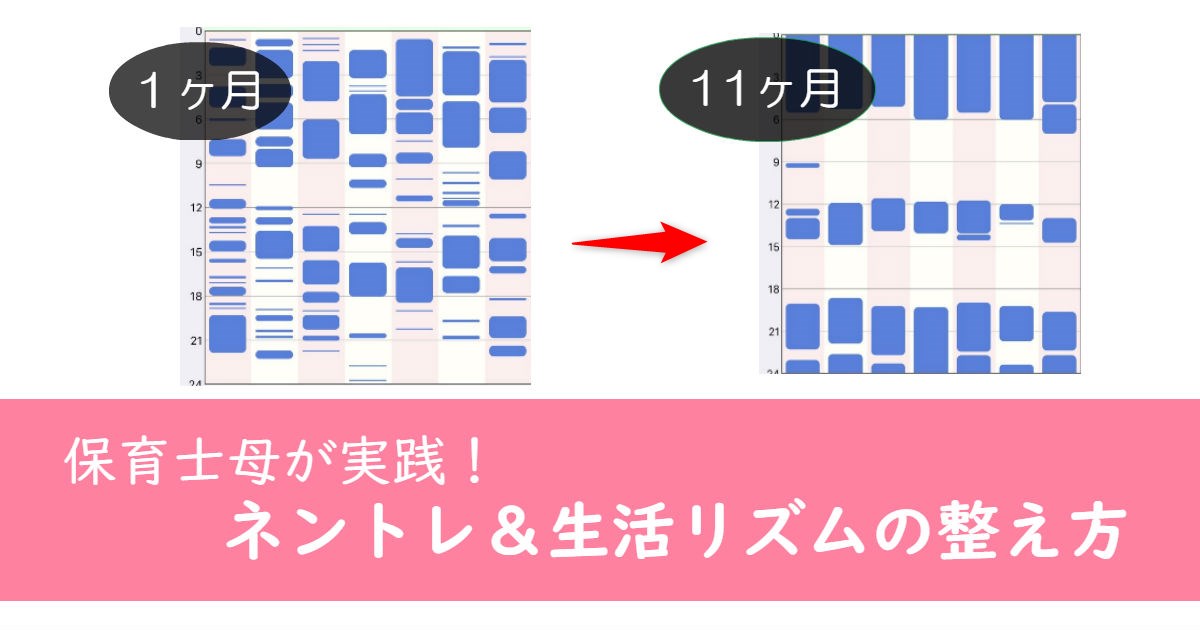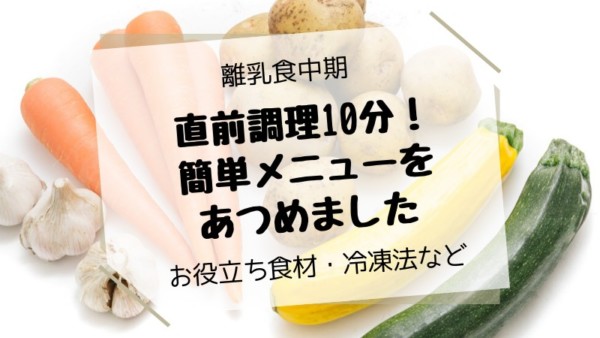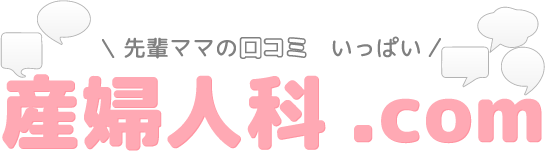次男が生まれてもうすぐ1年。
毎日ドタバタと忙しく、気がつくと「それはやめて!」「危ないってば!」など大声を出すことが増えていました。
そんなある日、長男が私の目をじっと見て、つぶやくように言った一言。
「おかあさん、おこんないで」
あぁ、このままではダメだ。我が子との関わり方を改めて勉強し直そう。
そう決めて手に取ったのが、以前Twitterで話題になっていた本「ADHDのペアレントトレーニング」です。(もともとADHDの子どもを持つ親のために書かれた本ではありません)
この記事には、ペアトレを実践したことで私と長男の関わりがどう変わってきたのか、実際の場面や、私の感じたことなどを記録しています。
ペアトレの進め方
長男から「おこんないで」と言われて反省したのは、自分の叱り方がキツすぎたり、言い過ぎだったりする自覚があったから。
じゃあどうすればいいのか?と考えるとまず「叱り方」が知りたくなりますが、ペアトレにはステップがあり、順番にひとつずつ進めていくことが推奨されています。
- 子どもの行動を3つに分類「してほしい行動」「してほしくない行動」「許し難い行動」
- してほしい行動の増やし方(肯定的な注目)
- してほしくない行動の減らし方(注目を取り去る)
- 子どもから協力を引き出す方法
- 許し難い行動に対しての制限の設け方
叱り方(してほしくない行動の減らし方)はステップ3までお預け。まずは子どもの行動を書き出して分類し、褒め方(してほしい行動の増やし方)を学ぶところからです。
まだるっこしい。早く先に進みたい。
でも数日間やってみると、これはやっぱりこの順番じゃなければダメなんだとわかってきます。
あなたは、はじめの部分をとばして制限を設けることやバトルプランを早く学びたいと思うかもしれません。しかしそれはあまりおすすめできません。この本で紹介する技法は、それぞれ前のステップで学んだ技法を知っておくことが必要だからです。
(略)
あなたがもっとも手をやいている行動に対処するには、その前にすべてのやり方を学ぶことが必要です。
ペアトレには本当に効果がある?本に沿って実践してみた
子どもの行動を3つに分類する
まずはじめは子どもの行動をよく見て、3つに分類するところから。
本文に「ノートに3つの欄を作りましょう」「最初の行に次のように書きましょう」と指示があるので、そのとおりに書いていきます。
分類する行動は自分が見たり聞いたりしたことから選び、できるだけ具体的に書くのが良いそうです。
| してほしい・もっと増やしたい行動 | してほしくない・減らしたい行動 | 許し難い・やめさせたい行動 |
| ✔︎弟におもちゃを渡す ✔︎母に「大丈夫?」と優しく言う ✔︎おもちゃを片付ける | ✔︎弟を押す ✔︎弟に「ダメ!」と強く言う ✔︎苦手な食べ物をつまんで取り出す | ✔︎人を叩く ✔︎怒ってオモチャを投げる |
子どもをほめる時は「肯定的な注目」をする
次に、リストアップした中の「してほしい・もっと増やしたい行動」を増やすため、子どもをほめる練習をします。
ほめるとは単に「すごいね」といった評価ではなく、励ましたり、見ているよというサインを出したり、「ありがとう」と感謝したりといった「肯定的な注目をする」こと。
- ほめる
- 励ます
- その行動に気づいていることを知らせる
- 感謝する
- 興味や関心を示す
そしてこれは何かが「できた」ときだけでなく「やっている間ずっと続ける」ことが大切とされていました。
- してほしい行動をはじめたとき(パジャマを脱ぎ始める)
- 多少まちがっていても、してほしい行動をしようとしているとき(靴を左右反対に履こうとしている)
- 指示にすぐ従っているとき(もう寝る時間よ、と言われて寝室に向かう)
- してほしくないことと反対のことをしている(叫ばないで静かな声で言う)
本には「(実践すれば)あなたとこどものふたりの関わりが、らせん階段を登るときのように、よい方向に向かってぐんぐんと進んでいきます」とありました。
いやいやそんなうまくはいかないっしょ・・なんて思いながら、実際に子どもに声をかけ、時間と内容を記録していきます。
| 時間 | 子どもの好ましい行動 | どうほめたか |
| 7:00 | オムツをゴミ箱に入れる | 「ありがとう」と目を見て言う |
| 8:00 | 「次男くん、おててどけて」と言う | 「優しく言ってくれてありがとう」と言う |
| 9:00 | 母が次男を抱っこしているのを見て「ぼくものりたいよ」と言う | 「ちゃんとお口で教えてくれてありがとう」と言う |
| 10:00 | おもちゃを投げようとしたが寸前で止めようとする | 「投げないで我慢できたのすごい!」と言う |
すると。
長男の場合、これがもうビックリするくらい即効性がありました。
今までもできるだけ「すごいね」「見てるよ」と声をかけてきたつもりだったのですが、改めて意識するとまったく違ったようです。好ましい行動が格段に増え、長男も私も笑顔で過ごす時間が増えました。
はじめは半信半疑でしたが、やってみるとどうやらこの「書く」という行為に大きな意味があるようです。
意識して子どもをほめるタイミングを探すようになり、それによって子どもの行動ひとつひとつが見えてきます。
これだけで生活がかなりスムーズに回るようになりました。
プロセスをほめることによって、あなたは肯定的な光を当てて子どもを見はじめます。
なぜなら、あなたは、小さな達成・正しい方に向かう小さなステップを探し、見つけ、これまであたりまえのこととみなしていた行動に気づくからです。子どもの方は、認められている、もっと協力したいと強く感じるようになるでしょう。
してほしくない行動を減らすには「注目しない(無視する)」
ほめ方・注目の仕方を実践した後は、ついに「してほしくない行動を減らす」場合。子どもの行動に注目しないようにし、自分の注意をそらします。
このやり方に関して、本文では「無視する」という表現が使われています。
無視というととてもひどいやり方に感じますが、説明をしっかり読めばなるほど納得できるものでした。
罰するために子どもを黙殺するのではありません。あるいは非難しているのを思いしらすために不機嫌になったり腹をたてているのでもありません。「これは私がしてほしくない行為です。この行為が続くかぎり、あなたはなんの得もしないし、注目もしてもらえませんよ」というメッセージを伝えているのです。
「無視」する際は怒らずうんざりせず、普通の態度を貫きます。そして、子どもがやめた時・してほしい行動が現れた時はすかさずほめるようスタンバイ。
こちらも記録を取っていきます。
| してほしくない行動 | どのようにして無視したか | 何をほめたか | どのようにしてほめたか |
| 怒っておもちゃを蹴る | 「蹴っちゃうならこっちに行ってね、話ができるようになったら教えて」と言って寝室に連れていき、その場を離れる | 「お話しする」と自分で言いにきたこと | 「自分で決められてすごかったね」と伝え、抱っこで話を聞く |
| 机に足を乗せる | 「やめて」と伝え、体をそむける | 足を下ろして違う遊びを始めたこと | 「さすがだね」と伝えて一緒に遊ぶ |
この方法で長男と向き合い始めて数日経ち、今までのように「声を荒げる」ことがなくなっていることに気がつきました。
大きな声・怖い言い方でなく「普通に」ただそのやり方は通用しませんよ、という意志を持って淡々と伝える。してほしくない行動が消えたときにはきちんと注目し、笑顔で接したりお礼を言ったりする。
これだとドガーンと怒る必要がないので、今までと比べると消費する労力は半分以下です。ちょっと楽している気すらしてしまうくらい。
それなのに今までよりはるかに落ち着いて笑顔の多い生活ができていることに気づいた時、大きな衝撃というか、ショックを受けました。
- 言いすぎだという自覚はあったけれど、それでも心のどこかで「ある程度ピシッと叱るときも必要」なんて思っていなかったか?
- その考え方自体、自分のイライラをぶつけるための正当化・言い訳だったんじゃないか?
長男に申し訳ない気持ちと、今気づけてよかったという気持ちと。このショックと反省を忘れないよう、今この記事を書いています。
許し難い行動には「制限を設ける」
許し難い行動(例えば人をたたく・怒ってオモチャを投げるなど)に対しても、基本的には上記と同じ「注目しない」で対応します。
紹介されている方法をひとつずつ試し、それでもどうしてもやめられないようなら「制限を設ける」ことになります。
ペアトレを実践してみて今思うこと
毎日少しずつ本を読んで関わりを見直すようにしていますが、初めてからまだ日が浅いこともあり、ふっと意識が抜けてしまっているときもあります。
そうすると、自分でもびっくりするくらい「うんうんそうだねー」なんて気のない返事をしていたり「もうそれはいいから」「それはやめてってば」なんて小言を言ってしまったりします。
自分の中に根付くまでくりかえし本を読み、長男と、そして自分と、しっかり向き合っていきたいと思います。
まだ長男が「おこんないで」って言う時はあるんだけど、自分が落ち着いてるから「怒ってないよ、でもこれはやめてほしいな」とか普通に伝えられるんだよね。
大きい声を出すことで私自身が興奮状態になってたのかもしれない。「ダメ!」「やめて!」に支配されて、自覚以上にパニクってたというか。
— ヒナ@3才長男と10ヶ月次男 (@hinamama_cm) July 30, 2020
端的に知りたい方は「発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル」もオススメ
今回参考にした「ADHDのペアレントトレーニング」はワーク形式なため、とても勉強になる反面、読みづらい・実践しづらいという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方には「発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル」がオススメ。
こちらはペアトレの本ではありませんが、似た内容がたくさん出てきます。文字が大きく端的にまとめられているので、とにかく今何かヒントがほしい!という時にきっと役に立ちます。